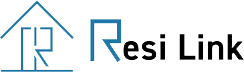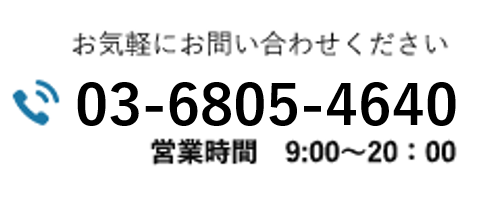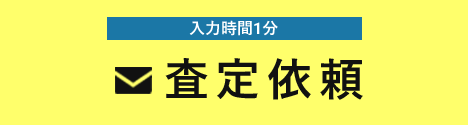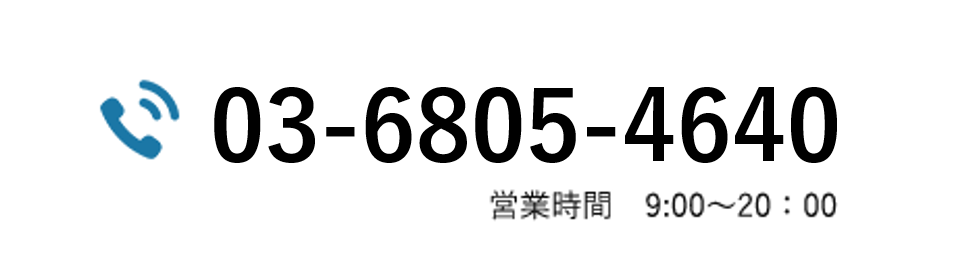離婚とともに家を売却をするときの流れは?注意点や大切なポイントを解説コラム
離婚とともに、不動産の売却を検討する方は決して少なくありません。
しかしその際に、
・残債のローンの支払いはどうなるのか?
・離婚後、家を売却する際の流れは?
・家の売却は名義人以外に行うことはできる?
などの様々な悩みが湧いてきますよね。
今回は、そのような離婚後に家の売却を検討する際に気をつけるべきことについて、解説していきます。
離婚後に家を売却する際の流れ
離婚が決まり、家の売却が決まるまでの一連の流れについて解説していきます。
家を売却すると決めたあと、名義確認や査定などのさまざまな工程を経て、初めて金銭として売却可能です。
しかし、財産分与する際に、夫婦間の金銭トラブルへと発展してしまうケースも十分考えられます。
トラブルを回避するためにも、ここで解説するポイントを押さえておきましょう。
①持ち家及び住宅ローンを組んでいる「名義」を確認する
まず初めに、所有している不動産、および組んでいる住宅ローンの名義人が誰なのかを確認しましょう。
原則として、所有している不動産の売却は、名義人にしか行うことができません。
例えば、所有している不動産の名義人が夫だけの名義であった場合、妻の意思で売ることはできません。
また、夫婦での共有名義の場合は、双方の同意が得られない限り、共同でなければ売却は不可能です。
不動産の売却権利が誰にあるのかを把握するために、最初に名義人の確認を行いましょう。
②不動産会社に住居の査定を依頼する
次に、現在の家の価値を調べるために、不動産会社に家の査定を依頼しましょう。
実際に家を財産分与をするにしても、家を売った代金でローンを完済できるかどうかを調べるにしても、実際に売却した際の価格がわからなければ次の段階に進めません。
現在の家の価値を知るためには、不動産会社に査定を依頼して、調査をしてもらいましょう。
ただし、不動産会社も依頼があった際に、売却を任せてほしいという理由で、価格を高めに見積もる場合もあります。
査定額を評価して正しい金額かを調べるためにも、複数の不動産会社に依頼をして、金額を比較して確認しましょう。
また、離婚の事情を詳しく話したくないなどの理由がある場合、机上査定という方法もあります。
机上査定であれば、家の中を実際に確認しないため、簡単に査定を依頼できます。
一方で、渡した情報だけで査定を行うため、価格は必ずしも正確ではない点には注意が必要です。
③売却するための活動を開始する
名義人の調査や不動産会社による査定が完了したら、具体的な売却のための活動を開始しましょう。
まずは、不動産会社と媒介契約を交わして、売却する家の購入希望者との仲介をしてもらう契約をします。
個人間でも売買は可能ですが、大きな金額のやりとりとなるため、トラブルになりがちです。
一般的には、不動産会社が窓口となり売却を進めることによって、トラブルを回避しながら売却活動を行えます。
無事に購入希望者を見つけ、新たな家の購入者に売却が完了したら、その金額を夫婦間で財産分与します。
④当事者同士で財産分与を行う
売買が完了した金額について、財産分与を行います。
割合や金額については、事前に打ち合わせることは可能ですが、その際に決まった内容や取り決めについては、公正証書や離婚調書として正式な記録を残すようにしましょう。
口約束で決めた内容は後日金銭トラブルの原因になりかねないので、証書に残すことで回避できます。
また、公正証書は法律のプロである公証人が作成する書面になるため、法律に基づいた書面として、離婚後のトラブル防止にも役立ちます。
離婚で家を売る際に気を付けるべき注意点
続いては、離婚とともに家を売却する際に注意が必要な点について、解説していきます。
ここで解説する注意点は、いずれも売却を検討する際に必ず守る必要があったり、確認が必須であったりするポイントばかりです。
売却を検討し始めた時点で、常に意識しておきましょう。
残っている住宅ローンの額を確認する
売却を検討するにあたり、住宅ローンの残債額を必ず確認しましょう。
そもそも、住宅ローンが残っている状態では、家を売却できません。
残債額を把握できていない状態では、いくら返済が必要かも不明です。
必ず残債額を確認して、ローン完済までの道筋を立てた上で、売却額の設定などを行いましょう。
家の売却を行えるのは名義人のみ
家の売却を実際に行えるのは、家の名義人のみです。
例えば、名義人が夫の家を妻の意思で売却することはできません。
原則として、家の契約をした名義人に売却をする権利があるため、名義人以外の人物による売却などの手続きは不可です。
必ず名義人からの売却でないと、手続きはできないため注意しましょう。
また、共同名義人として家を購入している場合は、双方の名義人の売却の意思が確認できない場合、同様に売却不可であるため、注意が必要です。
住宅ローンが完済していないと原則名義変更はできない
住宅ローンの名義変更は、原則はできません。
住宅ローンは、契約をする人の収入や勤務先、他社への借入状況などを審査したうえで、融資する金額を金融機関が決定します。
そのため、住宅ローンを契約している状態で名義変更をすることは、金融機関がその名義人の変更を認める必要があるため、かなり難しいと考えられています。
ただし、例外として住宅ローンが完済していない状態でも、名義変更を認めてもらえるケースもあります。
例えば、ペアローンとして住宅ローンを組んでいる夫婦が、離婚を理由に住宅ローンを単独名義に変更したいケースなどです。
この場合、金融機関に認められるだけの安定したローン返済能力を持っていることが必須の条件になります。
さらに、名義変更を認めてもらいやすくするためには、購入した家に名義人が住み続けることが大切です。
これらを守れれば、ローンが完済していない状況でも名義変更できる可能性があります。
住宅ローンが返済できないと家は売却はできない
住宅ローンを最終的に完済できない場合、家の売却はできません。
ローンが残っている状況で家を売却するためには、引き渡しの時点でローン完済が必須です。
もちろん、家を売却して手元に入ってくるお金で、ローンの返済をすることは可能ですが、完済はできないと言われています。
理由としては、一般的に住宅ローン返済スピードよりも、住宅の価値が落ちるスピードのほうが早いからです。
そのため、家の売却を検討する際は、自分の物件を売りに出す前に、これからかかる費用と、残りいくら支払う必要があるかを把握したうえで売却を行うようにしましょう。
住宅ローンが残っている場合の売却戦略とは
夫婦がともに購入したマイホーム。
離婚という形を選んだら「今後どのように処理するか」について徹底的に話し合うことが大切です。
「売却する」と決めた場合でも、住宅ローンが残っていると複雑な問題が絡んできます。
法的な課題も多く、「売れるなら売ってお金にしよう」と簡単にはいかないこともあります。
そこで、離婚で家を売却する際の売却戦略や対策をご紹介します。
現在のローン残高と売却予想額を調べる
住宅ローンが残っている場合、初めにやるべきなのは現状の確認です。
現在のローン残高や売却金額によって、今後の売却の戦略が異なってくるからです。
住宅ローンの残高証明書などが手元にあれば、現在でどのくらいの返済額が残っているかをチェックしましょう。
ローン残高を調べることにより、「いくらで売れば完済できるか」の目安が分かります。
次に、売却予想額を調べなければなりません。
いくらで家が売れるかは、
・築年数
・家の規模、間取り
・立地
・デザイン
・劣化の状況
・リフォームの有無
・接道の状態
・建ぺい率や容積率など法的な制限
など物件の特徴によって大きく異なります。
売却予想価格は、周辺の取引実績を参考にすると大まかな目安は分かるかもしれませんが、「同じような間取り・広さ」でも状況は全く違います。
できるだけ正しく売却予想の金額を調べるには、査定してもらうことが大事です。
アンダーローンなら普通の売却が可能
“ローン残高”よりも売却価格が上回るアンダーローンは、売却代金でローンを完済できるため、通常の売却を選択することが可能です。
売った後に手元にお金が残れば、財産分与の対象として夫婦で分けられます。
マイナスとはならないため、「負債を誰が払うんだ」といった争い話にもなりません。
「家を売ること」自体に関しては大きな問題が残りづらく、話し合いもスムーズに進みやすいかもしれません。
ただ、買主が見つからないことには売却ができず、住宅ローンを支払いながら数か月~1年経過するケースも。
その間も住宅ローンの返済が必要なので、どちらがどの割合で払うかなども話し合うことが重要です。
オーバーローンなら“損失”に関する戦略が必要
オーバーローンとは、売却金額よりもローン残高の方が高く、家の売却代金でローンが完済できないことです。
ローンが残ったままでは家の売却ができないため、以下のいずれかの方法を考える必要があります。
方法①:貯蓄などで補填する
差額がそれほど大きくない場合は、貯蓄などの自己資金で補填できれば家の売却が可能です。
ただ、離婚による売却の場合、貯蓄そのものも“財産分与”の対象となってしまい、「どちらが多く出すか」「半分ずつ出すか」など、補填の金額割合で揉める可能性があるので慎重に話し合いをしましょう。
方法②:任意売却という方法を選ぶ
売却代金でローンを完済できないときでも家を売れる方法が「任意売却」です。
通常、住宅ローン支払い中は、物件を担保として抵当権設定がされています。
末梢するには一括返済しかありません。
ただ、金融機関から「返済が残る」という同意を得て売却する任意売却も選択肢にできます。
売却後に残ったローンは、その後、払い続ける必要があります。
離婚後もローン返済が続くため、財産分与の金額や、今後の責任負担などで揉めてしまう可能性もあるでしょう。
離婚でオーバーローンになったときの選択肢にもできる任意売却ですが、実は難しい内容も含まれます。
金融機関だけでなく、任意売却に精通している不動産会社、財産分与も絡めて相談できる弁護士などのサポートが不可欠です。
方法③:どちらかが“住み続ける”という選択も
オーバーローンとなるときは売却をせず、離婚後も「どちらか一方が住む」という選択肢も選べます。
パターンとしては、
①名義人が住み続ける
②配偶者名義の家に、名義人ではない方が住み続ける
③共有名義でどちらかが住み続ける
などがあります。
名義人が住み続け、今後住宅ローンの支払いも続ける場合はシンプルですから、問題が起こりづらいかもしれません。
しかし、慰謝料の代わりに「名義人ではない側が住む」といったケースでは、トラブル事例も多いので注意が必要です。
出ていった方の名義が残ったまま片方が住むことで、
・勝手に売却されてしまうリスク
・ローンを滞納されて競売にかかるリスク
などもあります。
だからといって、賃貸のように「元配偶者に直接家賃を支払う」といった方法にしても、元夫婦という関係上、トラブルがつきまといます。
任意売却は選択肢のひとつではありますが、離婚後もさまざまなトラブルが待ち受けるリスクは多く、あまり現実的なものとは言えません。
専門家も利用して話し合う
離婚をする背景にはさまざまな事情があるかと思います。
そこにお金のことが絡んでくると、一層揉めます。
特に、住宅ローンが絡んだ不動産売却では、「利益をどんな分け方にするか」「マイナスとなったら誰が補填するか」など口約束だけでは大きなトラブルが発生しがちです。
お互いに「言った言わない」で、感情的に話をするとこじれます。
財産分与を進めるうえで、お互いに納得してしっかり協力し合わなければ、早期の売却も難しいかもしれません。
・財産分与や書類の作成は「弁護士」
・家の査定や売却依頼は「不動産会社」
・今後の資金計画やローンのことは「ファイナンシャルプランナー」
など、それぞれ専門知識に精通した専門家の力も借りながら進めることをおすすめします。
住宅ローンがない家なら売りやすいの?
残債がある場合と違い、住宅ローンが残っていなければ、問題点が少な目で売りやすく感じるかもしれません。
そこでいくつかのポイントをお伝えしていきます。
買取で売却して現金を分ける方法もあり
すでにローンを完済している場合は、普通通りの売却の他、不動産会社が直接買い取る「買取」という方法も検討できます。
相場と比べると買取の金額は低めとなりがちですが、「早く手放して現金化ができる」のはメリットです。
特に、相続や離婚など売却タイミングを早くしたいといった事情があるときは有効な手段となるケースもあります。
仲介売却には課題もある
一般的な仲介による売却は、
・物件によっては数か月以上かかる可能性がある
・いつ売れるか分からない
・内覧のためにハウスクリーニングやリフォームが必要なことも
・売れるまで夫婦の感情的な揉め事を引きずりやすい
などの課題もあります。
買取ならスピーディーに現金化できて問題解決に進めます。
売却完了までの“空き家期間”についても話し合いが必要
離婚後、お互いに住み替える場合は、売ろうとしている家は空き家になります。
建物は空き家になると傷みやすいため、定期的な管理も必要です。
・維持管理の手間と時間
・固定資産税の支払い
・売れるまで“元配偶者”との連絡を取り合うこと
が負担に感じやすいでしょう。
こういった状況では、「買取で売る⇒現金化して清算する」という方法により、揉め事を最小限にとどめ、関係を断ち切りやすくなります。
好条件の物件なら仲介の方が良いケースも
「立地が良い」など好条件の物件の場合は、一般的な売却でも早く高値で売れる可能性もあります。
ハウスクリーニングやホームステージングなどのサービスを利用するのも高く売るためのコツです。
信頼に値する不動産会社を選ぶこと
「早く売りたい」と期間重視の売却なら、買取が向いています。
ただ、「時間に余裕がある・少しでも高値で売りたい」場合は、売主と買主間で価格交渉ができる一般的な売却の方が向いているケースもあります。
しかし、最短で売りたいからと大切な資産を極端に安い金額で提示された結果、後悔することもありますので注意が必要です。
仲介による売却、買取による売却のどちらを選ぶにしても、信頼できる不動産会社の存在は欠かせません。
「大手だから安心」とは言えず、離婚など特有な背景による売買契約の実績が豊富な不動産会社を探すのもポイントです。
スムーズな連絡や親身になって相談してくれるなど見極めて依頼しましょう。
離婚で家を売却する際、財産分与はどのように計算するのか
家を売ったお金も財産分与の対象となるケースも多く、どのように計算するのか気になりますよね。
財産をどのように分け合うのかは、状況によって異なるものですが、よくあるケースやポイントをお伝えします。
夫婦の共有名義の家の売却
夫婦の共有名義の不動産を売却して利益が出た場合、通常は法務局にて登記された“持分割合”に応じて利益を分けることができます。
たとえば、
・売却して得た利益⇒2,000万円
・持分⇒夫:1/2 妻:1/2
という共有状態なら、1,000万円ずつの分配が基本的な考え方です。
夫、もしくは妻の単独名義の家の売却
どちらかの単独名義の不動産売却なら、売却代金は「名義人」が受け取ることができます。
たとえば、「結婚前に夫が全額出して購入した家」「妻が独身時代から保有していた家」など、婚姻前にすでに費用も払い終えていれば受け取る権利があるのは“登記上の所有者”です。
ただし、状況によっては、財産分与の対象になることもあります。
財産分与は登記簿謄本の名義や持分だけでは行われない
家の売却時、財産分与で調整されるのは、
・結婚後に2人で買った家
・婚姻期間が長い
・夫婦が共働きで住宅ローンの返済をしていた
・夫、もしくは妻が頭金を多く出していた
・夫は仕事、妻は家事や育児で家庭を守っていた
などの要素です。
お互いに家を買う背景にそれぞれの貢献度があった場合には、財産分与の対象として慎重に話し合うことが必要となるでしょう。
特に、住宅ローンの支払いだけでなく、購入時に「親や親族からの援助があった」なども考慮されるべき点です。
税金関連も忘れずに
売却益が出た場合、一般的には「譲渡所得税」が課される可能性があります。
譲渡所得税は、売却代金から
・取得費⇒購入代金、購入時の諸費用
・譲渡費用⇒売却時の諸費用(仲介手数料、解体費用、測量費用など)
を差し引いたものが“利益”となり、この部分に対して課税されるものです。
譲渡所得税はかからない可能性がある
離婚で自宅を売る際、税負担が心配な方も多いでしょう。
ただ、「譲渡所得税がかからない・軽減できる」ケースは多いです。
理由①:購入や売却時の諸費用が差し引ける
購入したときの諸費用や、売却時の諸費用も売却代金から差し引いた分が“譲渡所得”です。
たとえば、「3,000万円で売れた」としても、購入時・売却時ともに経費がいろいろとかかっていた場合は経費として差し引くことで、利益部分(課税対象額)は少ない金額になります。
理由②:特別控除が大きい
通常、マイホーム売却では、譲渡所得から3,000万円までの部分を控除できるという「居住用財産の3,000万円特別控除の適用」といった制度があります。
つまり、
「売却代金-(購入価格+諸費用)-(売却価格+諸費用)」
の計算によって3,000万円以下なら、課税対象ではなくなるのです。
一般的な家の売却と同様に、離婚時でも「3,000万円の特別控除」は使えるため、税金はかからないケースが多いでしょう。
理由③:所有期間が長いと税率も少なくなる
税率は、「所有していた期間」に応じて異なり、
・5年以上所有していた家を売る⇒長期譲渡
・5年以下所有していた家を売る⇒短期譲渡
です。
5年以上所有していた場合は税率も低く、課税額もおさえられます。
「3,000万円特別控除」という節税制度の条件に合えば、税金はほとんどかからないかもしれません。
住宅を財産分与する際の重要なポイント
不動産の財産分与は、どの項目の中でも特に難しいと考えられています。
なぜなら、金額が非常に高額になることや、夫もしくは妻が住み続けるのか、それとも売却するのか決める必要があることや、ローンの返済問題など、今すぐに決められない項目が多いためです。
この章では、不動産の財産分与を検討するにあたり、チェックをするべきポイントについて解説していきます。
不動産のままでは整理できないため金銭に変えて整理する
まず大前提として、不動産のままでは財産分与を行えません。
そのため、不動産を一度現金化した後、整理をすることが大切です。
現金化をするにあたって、2つの方法があります。
一つは、不動産を売却して、その代金を分割する場合です。
この場合は、不動産会社に仲介を依頼して新たな買い手を見つける方法や、不動産会社に買い取ってもらう方法などがあります。
もう一つは、一方は対象の不動産に住み続けて、他方はその不動産の価値の半分を現金で受け取る方法です。
これは、不動産の査定などをうけ、金額を確定したうえで、その金額の半分を他方に渡します。
もちろん、家を売却するわけではないため、住む家は残り続けます。
双方の合意を得られる場合、この方法をとることが可能です。
しかし、いずれもローンを完済できていることが条件になります。
ローンが返済できていない場合は、家の売却額をローンの返済に充てる必要が出てくるため、注意が必要です。
住宅を売却する際に金銭に変換したら残債務の支払いに充てる
住宅を売却するにあたって、査定をして金銭に変換をしたら、残債務の支払いに財産分与の際に得た現金を充てましょう。
前提として守らなくてはいけないのは、ローンの完済が完了していない不動産は、そもそも売却できないということです。
もし、万が一ローンの支払いが完了していない状態で新しい買主に家が渡った場合、その住居は差し押さえとなってしまい、新しい買主は住めなくなってしまいます。
売却をするとなった場合は、ローンの完済が絶対の条件になるため、売却が成立して金銭に変換できたら、残債務の支払いに充てるようにしましょう。
金銭トラブルを避けるために双方で決めた事項を離婚協議書として証書にする
離婚によって不動産の財産分与をすると決まった場合、話し合って決まった内容を離婚協議書として証書化しましょう。
そもそも離婚協議書とは、協議離婚をする際に、夫婦間で決めた条件や決めごとを整理して確認するための契約書をさします。
特に、金銭に関する部分は、離婚がまとまった後になりトラブルになるケースがほとんどです。
双方に権利がある不動産などは、口頭で話し合ってまとまったとしても、実際に清算するとなった場合、トラブルにならないとは言い切れません。
金銭がかかわるような重要な内容の話し合いは、離婚協議書などの正式な証書を作り、極力トラブルを回避することが大切です。
まとめ
離婚に伴って家を売却する場合、まずは名義確認や査定を行った上で、実際に売却の流れに移ります。
また、家を売却する場合、住宅ローンが残っていると売却できない、売却できるのは名義人のみなどの注意点も理解しておきましょう。
金銭に関わる部分になるため、この記事の内容を意識しながら、より慎重に調整を進めていくようにしましょう。
弊社は世田谷区に生まれ育って30年の代表が対応致します。
そのため、地域ごとでの適正な価格の設定、地域ごとの住みたい人の特性を考えた打ち出しをすることで適正価格での早期売却を目指します。
まずは無料査定だけでもご相談ください
弊社は世田谷区に生まれ育って30年の代表が対応致します。
そのため、各地域ごとでの適正な価格の設定、各地域毎の住みたい人の特性を考えた打ち出しをすることで適正価格での早期売却を目指します。
まずは無料査定だけでもご相談ください